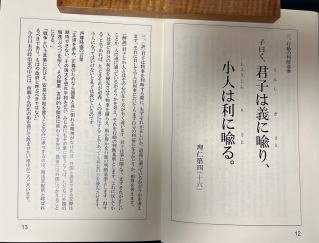
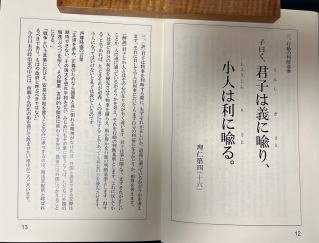
瀬戸塾創立40周年記念事業 武士道 論語読本 ※この論語は、瀬戸先生が毎月開催されている勉強会の 中で講話して下さった中から厳選した文章を載せています。 |
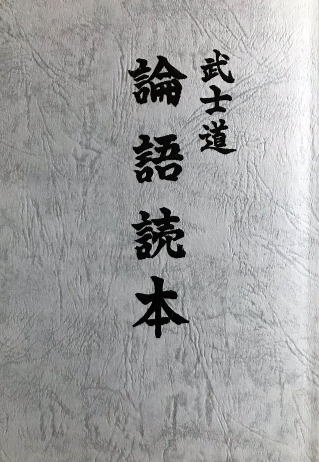 |
| はじめに 「論語」は、約二千五百年前の、支那大陸に活躍した思想家孔子の言葉を、彼の死後、弟子達が編纂した言行録であり、聖書と共に世界で一番読まれてきた書物の一つです。 孔子は紀元前551〜479年、支那大陸の春秋時代(紀元前770〜440)の末期を生きた人です。 人類文化の源とされる偉人、ブッダ(釈迦)、孔子、ソクラテスが同時代に出現したことは非常に興味深い出来事です。インドでは、ブッダ(お釈迦様)が孔子の生まれる12、3年前に、ギリシャではソクラテスが、孔子が亡くなる9年前の紀元前470年に生まれています。 釈迦、孔子、ソクラテスは世界の「三大聖人」、キリストを加えて「四聖」とも呼ばれています。彼等が生きていた紀元前5、6世紀に支那大陸に存在した約千八百もの封建国家が、春秋時代の末期には12〜15の代表的な国に統一され、これらの国が富国強兵を競い、戦乱、陰謀に明け暮れた時代です。 民衆は打ち続く戦乱と略奪に疲弊し、社会の秩序は崩壊し、人々の心は荒み、道徳は荒廃しきっていました。そういう時代に孔子は生まれました。 論語は文章と言うよりも一つ一つの文が短く完結していて、詩のような響きがあり、音読(声に出して読む)すると何か奥の深い知的な世界に誘い込まれるような気分になります。声に出して素読すること自体が則ち論語に触れるということで、言葉の力強さ、エネルギー、リズムなどが体全体に響き渡り、その情感が直接心と身体に伝わって来るからではないでしょうか。そして、心躍り、高尚な人間になれた様な気分になり学問に対して興味が湧いてくる。そんな不思議な力を論語は持っています。これは論語に限らず数百年の歴史に耐え、今もなお輝いている多くの古典、偉人の文章、言葉など全てに共通して言えることです。
孔子が最も重きを置いたのは、如何にして「徳を身につけるか。」です。孔子は、人はすべからく「徳」を身に付けなければいけない。特に人の上に立つ者は徳によって政治を行わなければ国は治まらないと説いています。 代表的な徳は仁、義、礼、智、信の五常が基本ではないかと思います。五常を学び身に付け、そして得た知識を実践する事で徳が身に付くと孔子は説いています。 |
|
| 武士道論語読本 著者 瀬戸謙介 定価 1,400円 仕様 A5サイズ P198 92の論語を解説。 ※この論語は、瀬戸先生が毎月開催されている勉強会の中で 講話して下さった中から厳選した文章を載せています。 |
|